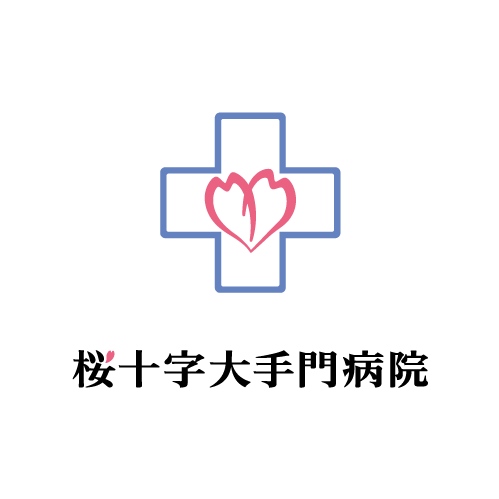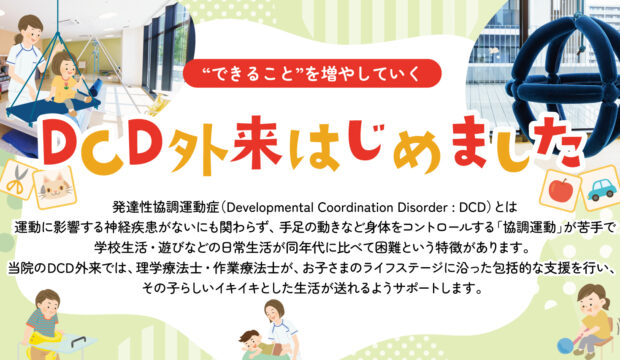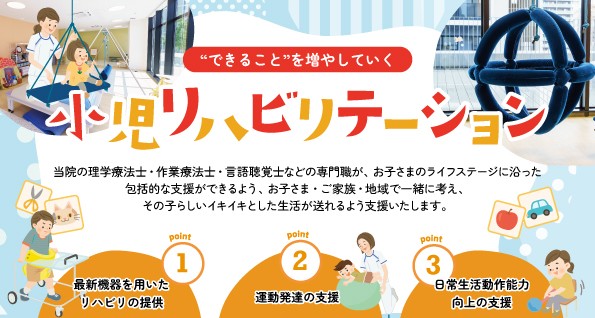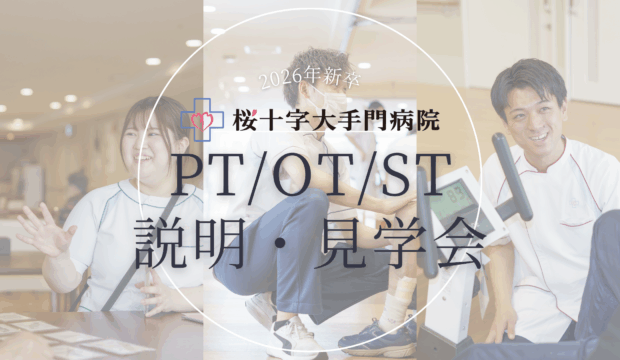先日、今年度入社の新入職員”金の卵19期生”を対象とした恒例の高齢者体験研修を、りすのこスクエアにて実施しました。
高齢者体験スーツを着用した新入職員たちは、視界の制限や関節の動きが制約された状態で、日常生活における様々な動作に挑戦。階段の昇り降りや、歩行訓練、車いす体験など、普段何気なく行っている動作が高齢者にとってどれほど困難であるかを身をもって体験しました。


体験後は、各班毎にレポートをまとめ、報告会をおこないました。
そのレポートの一部を紹介させていただきます。
新入職員の学びと気づき
<心理的影響について>
- 抑制体験では嫌な気持ちになり、忘れられるような感覚を味わいました。抑制は患者さまの尊厳や自尊心が損なわれることにつながると実感しました(新卒看護師)
- 高齢者体験で視野が狭くなると不安や恐怖を感じ、腰の痛みや疲労感から歩きたくない、疲れるのはイヤという気持ちが自然と生まれました。これが高齢者の方が外出を避ける理由の一つなのかもしれないと思いました(新卒理学療法士)
- 取り残されて苦しい気持ちになりました。抑制の苦しさを体験できたことで、患者さまの気持ちに少し近づけたと思います(新卒作業療法士)
<身体的制限の体験>
- 視野が狭く色が分からない、光がまぶしい、字が見えないなど視覚の制限を感じました。また声が聞こえにくく、ふたが開けにくいといった日常の些細な動作も困難でした(新卒医療事務)
- 首、腰、膝の痛みを感じ、歩幅が自然と狭くなりました。膝が上がらず、腕も思うように上がらない状態で、起き上がる動作さえ難しく感じました(新卒介護職)
- 高齢者の方の体の動かしにくさを実感することができました。普段何気なく行っている動作が、こんなにも困難であることに驚きました(新卒看護師)


高齢者への接し方で学んだこと
体験を通して、患者さまが安心できる接し方について多くの気づきを得ました。グループ発表では以下のような学びが共有されました。
<コミュニケーションの工夫>
- “あっち”など曖昧な声かけではなく、右や左など具体的な内容で声かけすることが重要
- 近くで大きな声でゆっくり話し、適度なトーンで明るく笑顔で話すことが安心感につながる
<安全への配慮>
- 物の距離感が分からないため、声掛けだけでなく誘導も必要
- 段差での声掛けを必ず行い、前もって次の障害物などを伝えることが大切
- 起床動作などの際、転倒リスクがあるためすぐに駆け付けられる距離で見守る
<心理的サポートの必要性>
- 視線を合わせることで相手を尊重している気持ちが伝わる
- 常に笑顔で接することで安心感を与えられる
- テレビが見えるところや人がいる場所、にぎやかなところに案内するなど、まずは抑制しない方法を考えることが大切


金の卵19期生は、今回の高齢者体験で多くの気づきを得ました。「高齢者の方々の身体的・心理的特徴を理解することで、より患者さま中心のケアを提供したい」「患者さまの尊厳を守りながら、安心して医療・介護を受けていただける環境づくりに貢献していきたい」など、前向きな声が多く聞かれました。
今回の高齢者体験研修を通じて、新入職員が患者さまの視点に立った看護・介護の重要性を理解し、より質の高い医療・介護サービスを提供できる人材へと成長することを期待しています。
金の卵19期生はこの経験を活かして、今週から“なりきり研修(他職種の業務を体験する現場実習)”へと進みます。高齢者体験で得た「患者さま目線」での気づきを大切に、今後の業務に取り組んでいただきたいと思います。
(Posted by 広報)